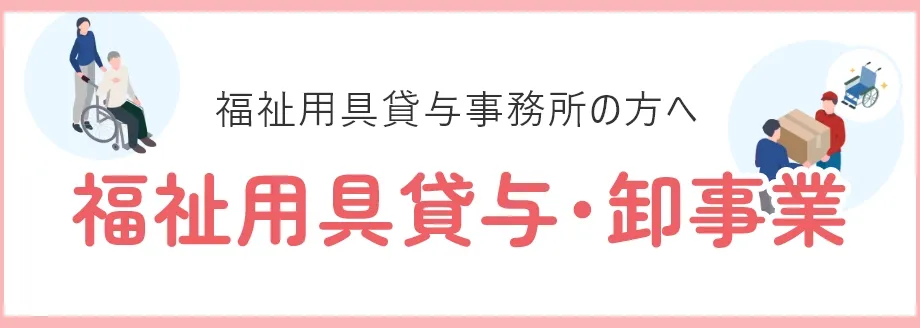ケアマネ朝比奈 第二話

-
-
-

朝比奈美鈴
「ケアセンターさくらの杜」に勤務する若手ケアマネジャー。
まっすぐな性格で、利用者と家族の想いを受け止めようと日々奮闘している。仕事への情熱と責任感が強く、時に自分を追い込みすぎてしまう一面も。
人の痛みに寄り添う優しさと、信念を貫く強さを併せ持つ女性。
-
 真田光
真田光杉並区にある介護ショップに勤める福祉用具専門相談員。
表情は穏やかだが、仕事における判断は的確で妥協を許さない。
利用者の生活に密着した提案に定評があり、冷静かつ現実的な視点を持つ。
-
-
-
 古賀忠司
古賀忠司
デイケア施設「アイリス」に勤める担当職員。
明るく気さくな性格で、利用者との距離が近く、場の雰囲気を和ませるムードメーカー。
仕事に対しては意外と真面目で、責任感の強さも見せる。
-
-
第二話


長机の上には書類の束と、湯気の立たない使い捨てカップ。時計の針は午後二時を指している。朝比奈美鈴は、いつも通り整然とノートを開き、すでに数本のペンを並べていた。
表紙にはうっすら手垢がついており、長く使い込まれた様子がうかがえる。彼女の癖は、話されたことすべてをメモに残すこと。要介護者の生活の質を高めるために、どんな小さな情報も見逃したくない。それが彼女の信念だった。

静かに周囲を見渡した後、朝比奈は口を開いた。「それでは......山口様のサービス担当者会議を開催します」彼女の声は澄んでいて柔らかく、しかし芯のある響きがあった。
斜め向かいの席で、真田光が無言で頷いた。背筋を伸ばし、手元の資料に視線を落とす。福祉用具専門相談員として三年目になる彼は、冷静でロジカルなタイプ。だが今日は、妙な緊張が胸を締めつけていた。

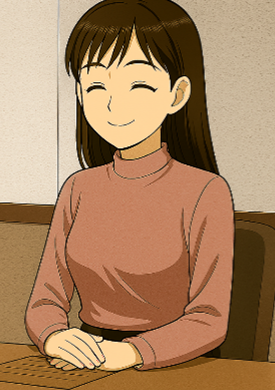
「最近、リハビリへの参加意欲が高まってきていましてね。週にもう一回、デイケアを増やしてみてはと思うんです。山口さん如何ですか?」
古賀の言葉に対して、ご本人もにっこりと笑ってうんうんと頷いている。
朝比奈は軽く目を見開き、山口様ご本人に向かってすぐに優しい笑みを浮かべた。
「それは......素晴らしいですね。変化が見えてくると、こちらも嬉しくなります」古賀は満足げに頷いた。
「ええ、前回ご利用のとき、ご本人が『リハビリで身体が軽くなる』と話してくれて」その言葉に、室内の空気がわずかに和らいだように感じられた。

だがその緩やかさの中で、真田の中の何かが音を立てた。
彼は唇を引き締め、朝比奈の手元のメモが止まる瞬間を見計らって、静かに口を開いた。
「朝比奈さん、私からもご提案を」
ホワイトボードに山口様宅の平面図と福祉用具の配置を書いて、提案を始めた。

「手すりの配置とベッドの向きを少し見直すだけで、山口様の起き上がり動作が格段に楽になります。こちらが、その配置図です」古賀の眉がわずかに動いた。朝比奈はホワイトボードを眺めながら、真田の方に身を寄せた。
「なるほど......すごく具体的ですね」
真田は頷きながら、さらに続けた。

その言葉で、山口様も身を乗り出してのぞき込んできた。机に並べられた棒人間のイラスト。トイレでの立ち上がり、ベッドからの移動、手すりから歩行器の持ち替え──シンプルで、しかし動きが明確に伝わる構成だった。
注※スティックピクチャーは人の動きを線で表したもの。
朝比奈の目が、ゆっくりと開いていった。やがて、その瞳が笑みを含んだ。
「これ......すごく分かりやすいですね。本当にありがとうございます、真田さん。とても助かります。山口さんどうですか。試してみませんか?」
スティックピクチャーを読み込んでいるご本人に問いかけると、「これはいいね、是非試してみたいね。こんなものまで作れるんだね。真田さんすごいね」と笑顔で応えてくれた。

だが真田は、その視線を感じながらも、冷静に資料を片付けていた。
彼もまた、古賀の想いに気づいていた。そして、自分の感情もまた、静かに芽を出し始めていることを認めざるを得なかった。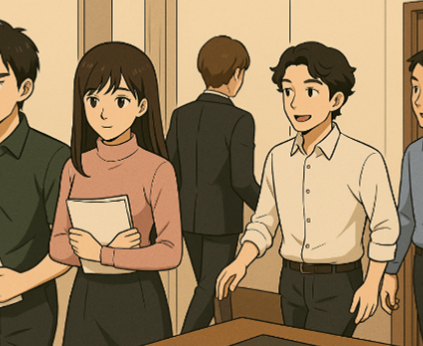
会議が終わり、スタッフたちが席を立ち始める。
「おつかれさまでした」と声をかけあい、空いたカップを片づけていく。
そんな中、朝比奈がそっと近づき、声を落とした。
「真田さん......あの......今日の資料、本当に助かりました。頼りにしています」
少しだけ息を飲んだ真田は、視線をそらしつつも、静かに頷いた。
「いえ......私のほうこそ、そう言ってもらえて嬉しいです」

「それと......事業所に壁掛け時計をつけたいんです。時間が分かりにくくて、他のケアマネも事務員さんも、ちょっと困ってて......。仕事には関係ないことで申し訳ないんですが......お願いしてもいいですか?」
その頼みは、業務の枠を越えた、個人的な信頼の証のように聞こえた。
真田は、ふっと微笑んだ。声も自然と、柔らかくなっていた。
「もちろんです。是非私にやらせてください。得意なんで」
二人の間に、短くもあたたかな沈黙が流れた。
それは言葉にならない確かなものを含んでいて、会議室の冷えた空気が少しだけぬくもりを帯びたように思えた。
心のどこかで、わずかに扉が開く音がした。
彼と朝比奈の距離は、ほんの少しだけ、しかし確かに縮まっていた。