Nコラム

成年後見制度とは、判断能力が不十分になった人の権利を守るために、法律上の代理人(後見人など)を家庭裁判所が選任する仕組みです。
対象は認知症や知的障害、精神障害などで判断力が低下し、日常の契約や財産管理を一人で行うのが難しい人。「判断能力」とは、契約内容を理解し、意思決定できる力を指します。認知症や障害でこれが低下すると、財産や生活に重大な不利益を受ける可能性があります。
制度は大きく分けて次の2種類があります。
任意後見制度:判断能力があるうちに、自分で将来の後見人を契約で決めておく制度
法定後見制度:判断能力が低下したあとに、家庭裁判所が後見人を選ぶ制度

成年後見制度の目的は、判断能力が低下してしまった本人の権利と利益を守ることです。具体的には次のような場面で活用されます。
・本人の財産を適切に管理する
・介護サービスや施設入所の契約を代理する
・悪質な詐欺や契約トラブルから本人を守る
・本人の希望を最大限反映し、生活の質を守る

成年後見制度は、本人の判断能力が低下した後に利用する「法定後見制度」と、将来に備えてあらかじめ契約しておく「任意後見制度」の2種類があります。任意後見制度の方が本人の意思を反映しやすく、比較的自由度も高い制度と言えます。法定後見と任意後見の2つについて、さらに詳しく見ていきましょう。
法定後見制度には「後見」、「保佐」、「補助」の3種類があり、家庭裁判所が医師の診断書や鑑定を通じて判断能力の程度を確認し後見人を選任します。それぞれ開始要件が異なっており、各種類の特徴については以下に解説します。
介護の契約や財産を管理するときに成年後見人に契約や管理をしてもらうことができます。交通事故などで保険金(損害賠償)を請求の必要があるときにも、後見人に本人に成り代わって請求してもらうことができます(代理権)。また、本人のした契約行為を後見人が取り消すこともできます(取消権)。
介護サービスなどを受ける場合、利用契約を結ぶ必要があります。その際、本人に代わって家庭裁判所に選任された保佐人に権限を与えることで、本人に成り代わって契約手続をしてもらうことができます。保佐の場合は、民法上に規定されている重要な財産に関しての行為に関して、保佐人の同意なく行うことができません。
医師から認知症などの症状があり、判断能力が低下していると診断され、本人一人で契約などが難しい場合、選任された補助人にサポートしてもらうことができます。もし誤った判断で契約してしまい、それを取り消したいときは、家庭裁判所に申し立てることで本人に代わって補助人が代理で行うこともできます。
| 後見 | 保佐 | 補助 | |
|---|---|---|---|
| 判断能力の状況 | 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者 | 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者 | 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者 |
| 開始の申立てに際し本人の同意を要するか | 不要 | 不要 | 必要 |
| 同意権・取消権 | 有 | 有 | (別途申立てにより)有 |
| 日常生活に関する行為以外の行為 | 民法13条1項所定の行為 | 民法13条1項所定の行為のうちの一部 | |
| 代理権 | 有 | (別途申立てにより)有 | (別途申立てにより)有 |
| 財産管理・生活の組み立てに関する法律行為 | 財産管理・生活の組み立てに関する法律行為の中から状況に合わせて選択した行為 | 財産管理・生活の組み立てに関する法律行為の中から状況に合わせて選択した行為 | |
| 本人の同意 | 不要 | 必要 | 必要 |
成年後見人になるためには特別な資格は必要なく、身近な家族はもちろん、弁護士、司法書士、介護福祉士などが成年後見人になることができます。ただ一般的には親族などの身近な人が後見人になることがふさわしいと言われています。これは本人の利益保護の観点や専門家に依頼することで費用がかかってしまうことを考慮してのことでしょう。また、未成年者、破産者、過去に成年後見人に選任されたが、家庭裁判所に解任された人などは成年後見人になることはできません。
本人に判断能力がある段階で、あらかじめ本人が選んだ任意後見人と自分の代わりにしてほしいことを契約で決めておく制度です。この契約を任意後見契約と呼び、公証人の作成する公正証書によって締結されます。本人が一人で決めることに不安を感じるようになった場合、家庭裁判所で任意後見人が選任され、任意後見契約の効力が発生します。
基本的に制限はありません。信頼できる家族、友人でも問題ありませんが、司法書士、弁護士、社会福祉士などの専門家のほうが望ましいでしょう。一方、未成年や破産者などは法定後見制度と同様、任意後見人になることはできません。

成年後見制度を利用するには、家庭裁判所への申立てが必要になります。法定後見制度と任意後見制度について、それぞれの申立てと手続きの流れについて具体的に説明します。
申立てに必要な書類
・申立書
・医師の診断書(判断能力に関する書類)
・財産目録、収支予定表
・親族関係図
申立て費用の目安
・収入印紙:800~1,600円程度
・登記費用:2,600円
・医師鑑定費用:5~10万円程度
法定後見制度の手続き
1.家庭裁判所に対する申し立て
家族か4親等内の親族の内の誰かを申立人として、家庭裁判所に後見開始申立ての手続きを行います。もし家族や親族がいない場合は市町村長などが申立てを行います。その際、手続きに必要な書類一式を家庭裁判所から事前にもらって作成しておきましょう。
2.家庭裁判所による調査と健闘
申立ての手続きが終わると、家庭裁判所の調査官が申立人と後見人候補者に面談を行います。調査では申立ての理由や本人の経歴、財産とともに後見人候補者の経歴も調べます。調査の結果は、本人の家族・親族に書面や電話で通知されます。
3.医学鑑定と面談調査
本人の判断能力や自立生活能力、財産管理能力などを専門医が医学鑑定します。また、家庭裁判所が本人と面談し、後見、保佐、補助の区分を確認します。
4.家庭裁判所による審判(法廷後見人の選任)
提出した書類、調査・鑑定の結果などを審査し、法定後見人を選定。申立人と後見人に審判書を送付し、法定後見制度の決定を知らせます。
任意後見制度の手続き
1.任意後見契約の締結
本人と後見人が任意後見契約書の内容を確認した後、公証役場に行き、任意後見契約公正証書の作成を依頼します。公証人は契約内容を把握し、公正証書任意後見契約書を作成。本人、後見人、公証人の3人が公正証書に署名し、任意後見契約が成立します。
2.任意後見監督人の選任申立て
本人の判断能力が衰えてきた場合、本人や家族・親族、後見人のいずれかが家庭裁判所に、任意後見監督人選任の申立てを行います。
3.家庭裁判所による調査と検討
家庭裁判所は診断書などを元に、本人の意思能力が不十分かどうかを調査します。
4.家庭裁判所による審判(任意後見監督人の選任)
適正であった場合は任意後見監督人を選び、その決定を通知します。任意後見監督人が正式に選任された時点から、任意後見人は契約書に従って後見人の仕事を開始することができます。後見人は後見監督人に、本人の状態や財産管理の状況を定期・不定期で報告します。
成年後見制度は認知症などで判断力が低下した本人の権利と財産を守るための大切な仕組みです。先々のことを考え、任意後見制度の活用などを視野に入れ、準備しておくことが大切です。また、成年後見制度だけでは生活のすべてを支えられません。地域の福祉サービスや相談機関と組み合わせることもまた重要です。
まずは「任意」と「法定」の違い、手続きの流れ、判断能力の基準を理解することで、より安心して将来に備えることができます。
日建リース工業は、介護現場に必要な介護用品・福祉用具を豊富に取り扱っており、ご利用者はもちろん、ご家族の方々にも喜んでいただけるケアレンタルサービスを提供しています。今回のように認知症などで判断能力が確認できない場合は、在宅介護をする可能性もあります。特にはじめての方は不安も多いことでしょう。そんなとき専門知識を持った担当が的確なアドバイスをし、ご利用者やご家族をサポートします。介護用品や福祉用具については、ケアマネジャー様が詳しいかと思いますが、もしレンタルやリースで迷っている場合は、日建リース工業を思い出してください。見積依頼も無料です。お気軽にご相談ください。

床ずれ防止用具・体位変換器
詳しく見る

特殊寝台・特殊寝台付属品
カタログ
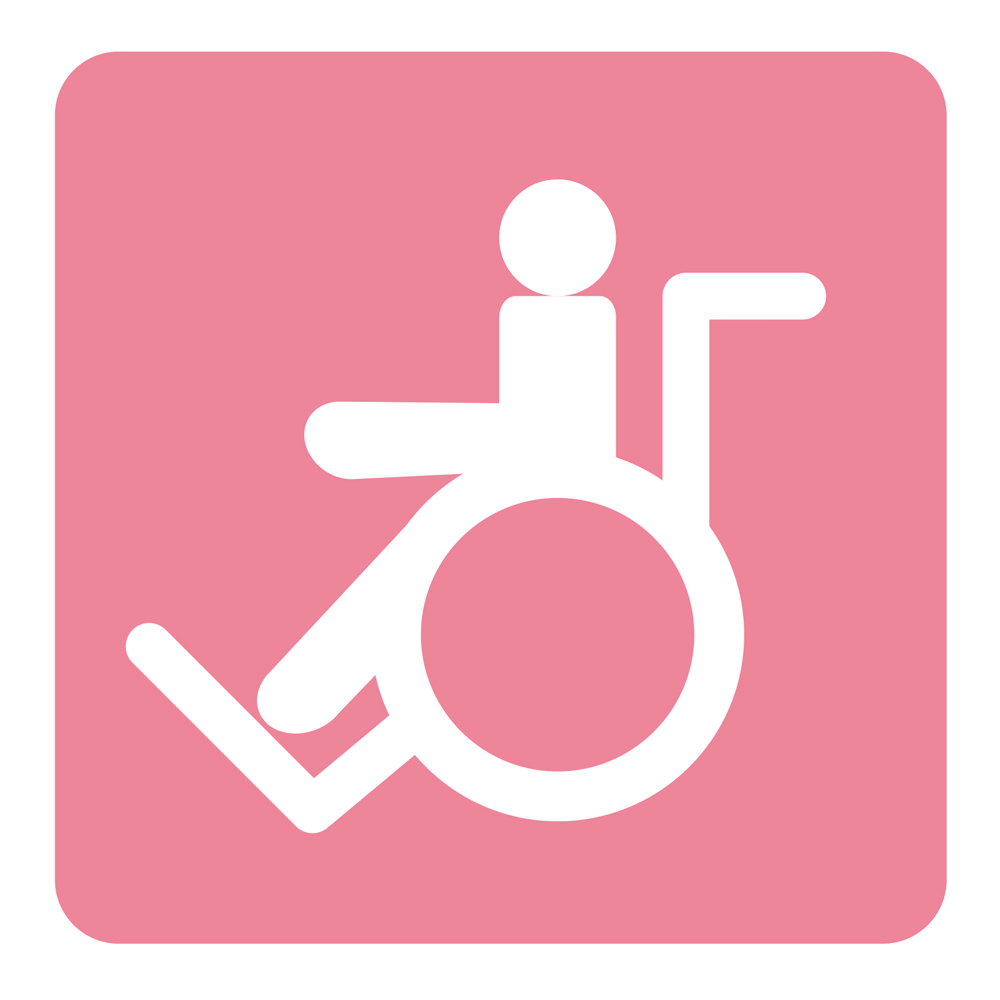
車いす、車いす付属品